
|
|
| 氷は溶けて水になり、さらに温度を上げると蒸発します。このように物質には固体(結晶)と液体と気体という3つの状態があります。私達の研究室で主に扱っている”液晶”とはこの3つに分類できない”第4の状態”のことを示しています。つまり前述の3つの状態は、 ★気体と液体は”密度”で区別される ★液体と固体は”流動性があるかないか”で区別される のに対して、液晶といわれる状態は”流動性がある”のに液体とは違う状態を言います。 詳しく言うと、分子は結晶状態で分子は整然として並んでおり、液体・気体の状態では分子は方向の規則性も失われてバラバラになっています。液晶状態は、分子の”重心の位置”がバラバラになりつつも分子の方向は規則性を保っています。(図1) |
| 結晶 | 液体・気体 | 液晶 |
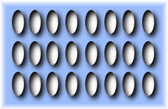 |
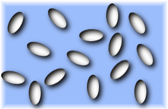 |
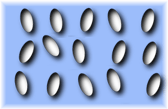 |
図1.結晶・液体・気体および液晶時の分子の配列状態
| 液晶の分子配列構造 |
| 液晶にはいくつかの状態があります。図2に示すようなz軸方向の位置の秩序を残したまま、xy面内の位置の秩序が失われた液晶を”スメクティック液晶”と呼びます。このスメクティック液晶は図1に示したような構造とは異なり”層構造”を持っており、層の中の位置の秩序が失われているのが特徴です。また、図1のような位置の秩序が消失している液晶を”ネマティック液晶”と呼びます。 |
| 図2.スメクティック液晶の層構造 |
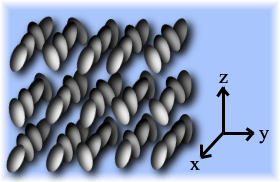 |
| 液晶の出現様式 |
| 液晶を示す分子は温度を上げてゆくに従って、固相→スメクティック相→ネマティック相→液体と変化します。液晶相が全く現れない物質や、スメクティック相が現れず、固相→ネマティック相→液相と変化するもの、液晶相の中で、ネマティック相が現れなかったり、いくつかのスメクティック相が現れたりするものがありますが、このような状態変化は温度変化によって起こります。このような液晶をサーモトロピック液晶と言います。現在、液晶ディスプレイに使われているのは全てサーモトロピック液晶です。液晶ディスプレイは常に液晶状態でなければいけないため、ディスプレイ用の液晶材料はディスプレイの使用温度範囲全体にわたって液晶状態である必要があります。液晶の温度範囲を広げるために、多くの液晶を混ぜることも重要な技術となっています。寒冷地などで液晶ディスプレイの反応が遅れてしまうのは寒さによって液晶の流動性が失われるからです。 |
| 小林研究室の今後のテーマ |
| 規則的に配向した分子集合系の中で起こる化学現象は、複数の分子間相互作用が同時に関与した協同現象の形をとることが多い。この協同現象の発現機構を分子間相互作用の観点から解明することは、各種生体機能の人工的再構築や機能性材料の開発を目標としている現代化学の基礎的な重要課題です。 私達の研究室では、この重要課題に挑戦することを視野に入れて、液晶やLB膜などの配向した分子系における分子間相互作用と分子配列に関する分光学的研究を構造化学的な立場から進めています。 研究の手法としては、分子の電子状態を扱う様々な実験的・理論的手法を用います。特に、分子間相互作用を敏感に検出できる電子吸収スペクトルや蛍光スペクトルなどの分光法を利用し、分子間相互作用が反映されたスペクトルデータを遷移モーメント間の相互作用モデル(Exciton Model)に基づいて理論的に解析することにより、分子間相互作用と分子配列の特性をスペクトルデータから抽出します。 主な研究テーマは以下の通りです。 |
|
1) 液晶(ホスト)−色素(ゲスト)系の協同的分子間相互作用に関する研究
|
|
2) リオトロピック液晶のミクロな分子配列と分子間相互作用に関する研究
|
|
3) リオトロピック液晶のマクロな分子配列の誘起とその応用
|
|
4) 配向した液晶中におけるゲスト分子の偏光吸収スペクトルの測定と解析
|
|
5) LB膜の分子配列・分子間相互作用とエネルギー移動に関する研究
|
|
6) 偏光ATR(減衰全反射)スペクトルによる界面領域の分子配向の解明
|
|
7) 電場による極性分子の配向制御と特異的分子間相互作用の発現
|
| また、平成15年度からは次世代ディスプレイ技術として注目されている有機ELについても研究を行っていく予定です。 |
| 有機ELについての研究 |
| 蛍光とは簡単に説明すると、光を吸収した分子がエネルギーの高い状態(励起状態)になり、その後、元の状態(基底状態)に戻ろうとする分子が放出する光の事です。有機ELは蛍光を示す分子を光ではなく、電気で励起状態にしようという技術です。有機ELの発光の仕組みは下図のようになっています。 |
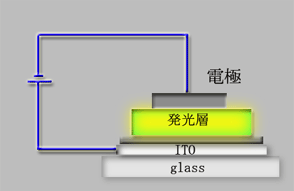 |
| 上の図は簡略化した図ですが、ガラス板の上に透明電極であるITOを蒸着させ、プラスの電気を流しやすくする正孔輸送層、発光層、マイナス電極を順に蒸着させています。この装置に電流を流すと発光層が励起状態になり蛍光を発します。現在、この発光のメカニズムは主に正孔と電子の衝突によって励起子が作られ、その励起子によって分子が励起されると考えられていますが、量子化学的な考察は殆どされていません。私達の研究室では、このEL発光のメカニズムを量子化学的な立場から考察することを目的としています。 |
●有機ELに関する研究
|
| TOP | OUR WORKS | PROFESSER | STAFFS |
| LESSON | AGU LINKS |