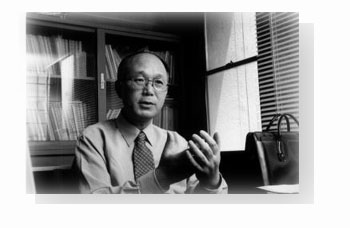| "化学現象は分子間相互作用の諸形態の現れである"-この信念が私の研究方針の底に流れる通奏低音です。化学現象の面白さ・奇妙さは,化学現象が孤立分子の性質だけでなく,分子集合系としての特性である分子間相互作用を反映していることに起因している。分子集合系の中で起こる化学現象は複数の分子間相互作用が同時に関与した協同現象の形をとることが多く,その最も複雑なものが生命現象である。現在,孤立分子と分子集合系との間には理解の仕方と精度に関し極めて大きなギャップが存在している。このギャップを埋めるためには,孤立分子について得られた知識・方法論を再統合して,協同現象に関わる複雑な分子間相互作用をも扱い得る方法論としての全く新しい独創的な一般則を生み出すことが必要であろう。私自身もこのことを常に肝に銘じつつ,さりとて天才みたいに天からの啓示を得ることは不可能なので,"一つの物質の中に全ての真理が宿る"ことを信じて,一つの物質が関わる化学現象と悪戦苦闘する中で,どんな些細なことでもよいから何らかの一般則を見出そうとたゆみなき考察を執拗に繰り返しながら研究を行っているつもりです。
分子間相互作用は分子の配向に強く依存し,方向性・異方性を有する。従って,複数の分子間相互作用が関与した協同現象が出現するためには,分子集合系は何らかの規則的な分子配向状態を有することが必須である。その様な配向した分子集合系として,リオトロピック液晶が各種生体機能に関連して現在特に注目されている。光合成における明反応,好気姓呼吸,視覚現象などの現象は生体の液晶構造に由来している。しかし,これら液晶の機能の背後に在る電子的・分子的機構の研究は殆どなされておらず,液晶の分子配向状態と,それに起因した分子間相互作用の方向性や機構を分子構造論的な立場から解明する基礎的な研究が重要となっている。
以上のように,規則的に配向した分子集合系の中で起こる協同現象の発現機構を分子間相互作用の観点から解明することは、各種生体機能の人工的再構築や機能性材料の開発を目標としている現代化学の基礎的な重要課題である。我々の研究室では、この重要課題に挑戦することを視野に入れて、液晶やLB膜などの配向した分子系における分子間相互作用と分子配列に関する分光学的研究を構造化学的な立場から進めている。 |